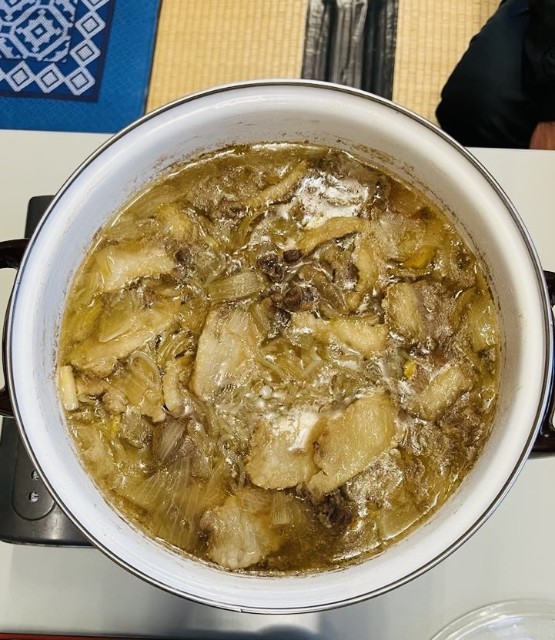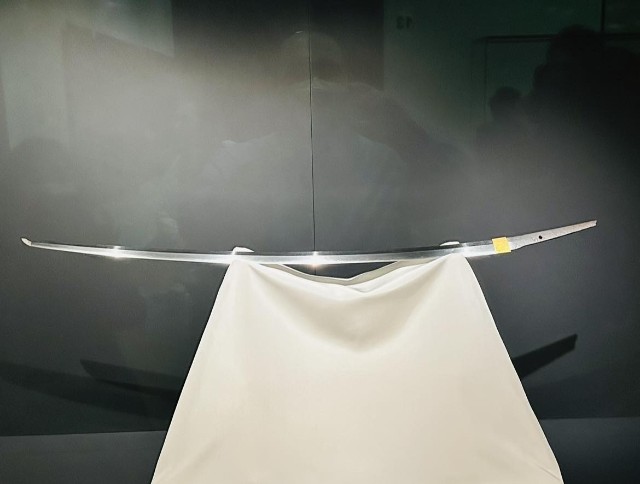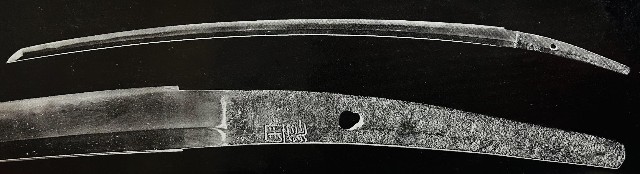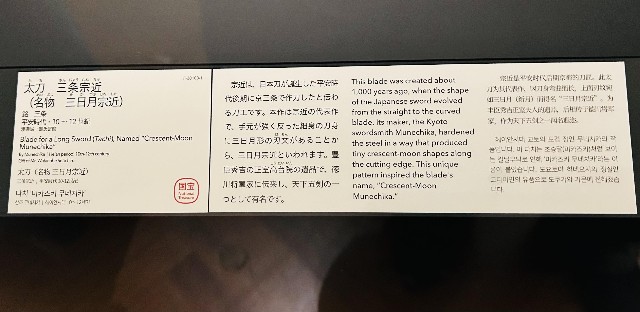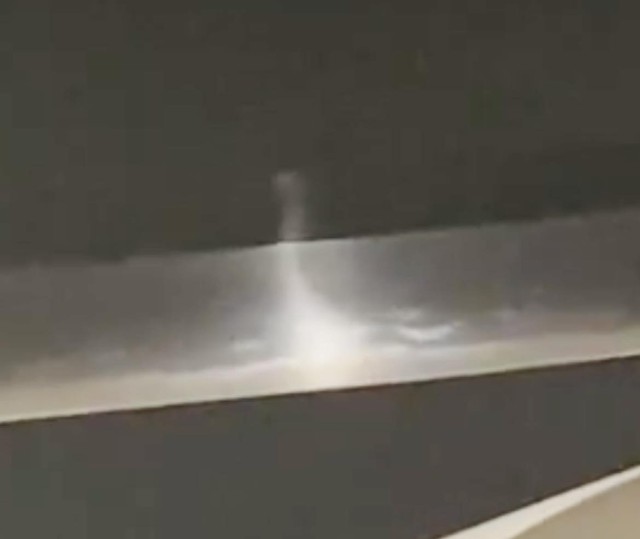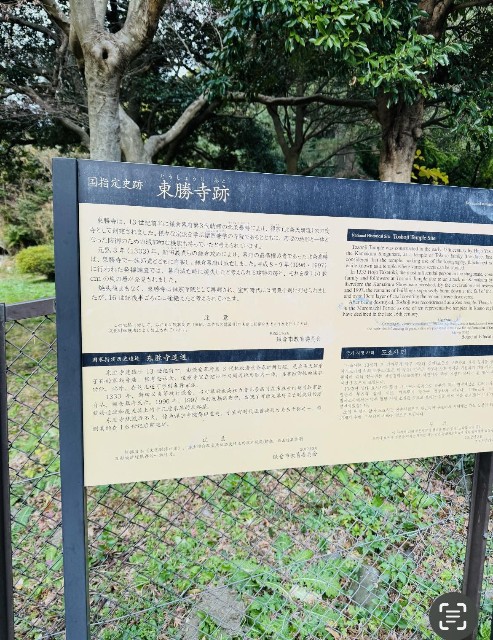先週は本流の雪代(ユキシロ)の多さにビビってしまって支流に入りました。支流もそれなりに釣れて満足したのですが、何となく気後れした自分が面白く有りませんでした。そこで今週は本流を攻めるつもりで木曽に出かけたのです。
本流と言っても上流部に入りましたので、まだ所々に水仙の花が綺麗に咲いてます。今回の木祖村と先週の上松町では大凡250mの標高差があります。先週の上松町は既にハナモモが咲いておりました。
雪代とは此の様に薄く白濁している事が多く感じます。一般的に水温が下がり過ぎてしまい活性が落ちると言われております。しかし釣り方によってイワナは釣れてまいります。
こっちは上松町の雪代が入ってない支流の水質です。春先に此のようになってしまうと逆に釣り難くなります。全く我儘なモノですね。
さて釣りの方は案の定で活性が低い状態でした。こういう時は流れの筋では食いません。大きな沈み石周辺を立ち位置を変えて丹念に攻めます。先週は水量が多過ぎて、石の前で止めて探る独特な雪代期の釣りが出来なかったのです。今週は水量が落ちた為に沈み岩がよく見えます。
岩の下から引き摺り出したのは此の3匹でした。驚いた事に皆んなメスです。産卵後に此処まで降り、体力を回復をさせていたのでしょう。真ん中のイワナはお腹がペッタンコでした。三ツとも測ったように9寸前後です。
第二ラウンドは木曽福島の行人橋辺りまで移動しました。此の時期によく入る場所です。15cmから18cmくらいのチビ達が釣れて来ますが、ハイシーズンに6寸以上で出会える事を楽しみにしてお帰り頂きました。
キープは8寸5分アマゴと6寸5分イワナの2匹です。木祖村の彼女達と比べてグラマーでした。今日は此れで納得致しました。帽子を取って木曽川の龍神さまに感謝した次第です。
帰りは何時も宮ノ越の南宮神社さまに御礼を申し上げて帰路に着きます。今日の南宮神社はとても柔らかい神気に溢れておりました。
南宮神社の駐車場から出て、国道に入ろうとすると、車のウインドウをコンコンと叩く音がします。『???』 何だろうと後ろを振り返ると後部座席の窓枠に『キビタキ』がとまっており、嘴でガラス窓を叩いております。
急いで撮影したのでボヤけてしまって申し訳有りません。
私は氏神さまの『使い』かと思って車外に出ました。辺りを見回してみても何も無かったので本殿に向かって拝礼致しました。キビタキさんは近くの木にとまってましたのでキビタキさんにも拝礼しました。そうしましたら『チチ〜チョ』とひと泣きしてくれました(笑)。
此の時期の木曽は綺麗です。もう時期山々が芽吹き、山吹の花が咲き乱れる事でしょう。コブシの白、山吹の黄色、山桜のピンク、そして何より噎せ返る様な新緑に覆われ、まるで水彩絵の具を敷いた白いバレットのようになるのです。そんな日を楽しみにして権兵衛トンネルを超えた次第です。